NHK『べらんめい』に触発されて語る、
書道職人55年の真実|
作品を残さない理由と明朝体練習法
NHK時代劇『べらんめい』が
呼び覚ました職人魂
先日、NHKの時代劇『べらんめい』を
観ました。
画面に映し出される書作品の力強さ、
セットに書かれた看板の文字——
その一つ一つに、職人の魂が
宿っているのを感じたのです。
筆の勢い、墨の濃淡、
紙に刻まれた一瞬の呼吸。
「ああ、これだ」
55年間書道に向き合ってきた
自分の人生と重なり、
この番組に触発されて、
ぼくも率直に語ろうと決心しました。
格好つけずに、飾らずに。
ぼく自身の書道人生を。
【書道歴55年】
作品を一枚も残さなかった理由
無我夢中で書き続けた日々
ぼくは書道を始めてから
55年が経ちます。
中学生の高学年の頃に
書道に取り憑かれてから、
ただひたすらに無我夢中で
書き続けてきました。
当時は放課後になると
書道教室に通い、
家に帰ってからも夜遅くまで
筆を握っていました。
墨の香りと半紙の感触が、
ぼくにとっての日常そのものでした。
友人が遊びに誘ってくれても断り、
テレビを見る時間も惜しんで、
ただひたすら筆を動かしていました。
親からは「もう少し休んだら」と
心配されるほど、
書道に没頭していたのを
覚えています。
これだけ長い年月、
夢中で書いてきたのだから、
さぞかし作品が残っているだろうと
皆さんは思うでしょう。
ところが、まったく
残っていないのです。
なぜなら、ぼくは書いた後に
破り捨ててしまうことが、
あまりにも多かったからです。
一枚書いては破り、
また一枚書いては破る。
その繰り返しが、
ぼくの書道人生でした。
展覧会で入賞しても
破り捨てた
読売書法展や各種書道展、
社中展の作品は、
確かに数多く書いてきました。
しかし発表が終わってしまうと、
自分の目で見て気に入らなくなり、
破り捨ててしまったり
人に譲ってしまうことが
多かったのです。
展覧会では入選や入賞を
頂いたこともありますが、
それでも作品を大切に
保管するという気持ちには
なれませんでした。
会場で飾られている
自分の作品を見ると、
すでに粗が気になって
仕方がなかったのです。
完璧主義だったわけでは
ありません。
ただ、自分の作品を
残しておくという発想が、
当時のぼくにはなかったのです。
書いた瞬間が最高で、
時間が経つと粗が見えてくる。
そんな感覚の連続でした。
書くという行為そのものに
価値があり、
完成した作品は既に
過去のものだと感じていたのです。
【書道上達法】
「下手くそ」と言われて
掴んだ練習の極意
朝晩の猛練習が
筆耕プロへの道
学校を卒業してからも、
先輩から「下手くそだ」と、
容赦なく言われていました。
そのため、相当に練習を
重ねました。
ただひたすら練習、練習、
また練習です。
朝は仕事に行く前に1時間、
夜は帰宅してから2〜3時間。
休日は丸一日、
筆を持っていることも
ありました。
その頃は一日に100枚以上
書くこともありました。
半紙の山が部屋の隅に積み上がり、
墨汁の消費量も
相当なものでした。
だから作品として残る物が
なかったのです。
練習で書いた物は
次々と捨てていきましたから、
手元に何も残らないのは
当然のことでした。
今思えば、
この厳しい練習期間があったからこそ、
後の筆耕の仕事で
通用する技術が身についたのだと
思います。
先輩の厳しい言葉も、
今となっては感謝の気持ちしか
ありません。
【筆耕のプロ】
仕事で学んだ書道の本質
筆耕とは何か
仕事では筆耕という、
ビジネス向けの書道を
専門にしていました。
筆耕とは、招待状や表彰状、
宛名書きなど、
依頼者のために筆で文字を書く
仕事です。
企業の式典用の賞状から、
結婚式の招待状の宛名書き、
感謝状や卒業証書まで、
様々な依頼をこなしてきました。
一日に何十枚、
時には何百枚もの文字を書くことも
あります。
そこでは芸術性よりも
正確性とスピードが
求められました。
失敗作だけが残った皮肉
特に結婚式のシーズンになると、
招待状の宛名書きだけで
数千枚を書くこともありました。
同じような文字を
繰り返し書く作業は、
一見単調に見えますが、
一枚一枚に心を込めることが
大切だと学びました。
仕事ですから、書いた物は
相手に(納品)渡してしまいます。
当然、作品としては
手元に残りません。
ただし、失敗した物だけは
残りました。
名前を間違えたり、
線の入り方が気に入らなかったり、
そういった失敗作だけが
手元に残ったのです。
※なんとなく取っておいていますが、
気に要らなければすぐにでも
捨ててしまいたいです。
この失敗作の山が、
ぼくにとっての唯一の
「作品集」かもしれません。
失敗から学ぶことの方が、
成功から学ぶことよりも多いと
実感しています。
【独自練習法】
明朝体を筆で書く——
26歳で編み出した上達の秘密
中学の美術とは
全く違う練習法
ぼくが筆耕を始めたばかりの
26歳頃、
ある独特な練習方法を
編み出しました。
それは、皆さんが普段使っている
「明朝体」を、
そのまま筆で書くという
練習です。
中学校では美術の授業で
明朝体やゴシック体を
書いたことがあります。
ただしそれはトレースという課題で、
方眼紙や物差しを使って
ズームアップし、
線の外側をなぞってから
中の空間を埋めるという
やり方でした。
機械的な作業で、
書道とは全く別物でした。
定規で線を引き、
コンパスで曲線を描く。
それは設計図を描くような作業で、
筆の持つ生命感とは
程遠いものでした。
新聞の明朝体を
筆で書き写す
筆耕での練習は違います。
新聞や印刷物の明朝体を
そのまま見ながら、
筆で他の洋紙に書き写していくのです。
新聞を見て、
その文字をそっくりそのまま
筆で書いていく、
そんな地道な練習でした。
使用した筆は小筆で、
墨は濃いめに磨って使っていました。
紙は練習用の半紙ではなく、
わざと表面がつるつるした
洋紙を使いました。
なぜ洋紙かというと、
筆耕の仕事では洋紙に書くことが
多かったからです。
実践に近い環境で練習することが、
上達の近道だと
考えていました。
洋紙は半紙と違って
墨の吸収が悪く、
筆のコントロールが
難しいのです。
だからこそ、
洋紙での練習が
実践的だったのです。
最初は新聞の見出しから始めて、
慣れてきたら本文の小さな文字も
書きました。
虫眼鏡で見なければ
わからないような細部まで、
忠実に再現しようと
努力しました。
【結論】
明朝体練習で得られた
「均一さを見る目」
この練習は
仕事では使えない
この練習は実際の仕事としては
使えませんでした。
明朝体は読むための物であって、
練習して書く物ではありません。
では何のために書いていたのかというと、
「均一さ」を学ぶためです。
実際にあなたも書いてみれば
わかります。
虫眼鏡でよく観察しながら、
点画の入り方、
字を四角く囲った時の線の長短、
すべてを細かく観察しながら
練習していきます。
特に注目したのは:
-
- 横線の長さの比率
- 縦線の間隔の均等性
- はらいの角度や止めの位置
- 印刷された文字の精密さ
- 明朝体の横線と縦線の
太さの違い、
ウロコと呼ばれる
三角形の装飾、 - 文字全体のバランスなど、
細部まで観察することで、
文字の構造が見えてきました。
気持ち悪いほど整った文字
完成した後は、
あまりにも整いすぎていて、
とても気持ち悪くて
見ていられませんでした。
この練習は1ヶ月ほど続けましたが、
当たり前ですがすぐに
飽きてしまいました。
明朝体は書いて練習する物じゃ
有りませんね。
しかし、
この練習で得たものは
大きかったのです。
文字の構造を客観的に見る目が
養われました。
字形のバランス、線の配置、
空間の使い方など、
書道の基本要素を
分析的に理解できるように
なったのです。
さすがにゴシック体までは
練習しませんでした。
グラフィックの文字は
所詮グラフィックです。
筆で書く文字は、
やはり古典からの積み重ねには
敵いません。
【書道の真実】
均一さは大切——
でもそれだけじゃダメ
明朝体が気持ち悪く感じる理由
仕事上、自分の名刺も人の名刺も
たくさん頂いています。
実はこのような経緯があるため、
ぼくは明朝体を見ると
少し気持ち悪いと感じて
しまうのです。
ただ、便利だから使っています。
こうやって文字を打っているのも
便利だからです。
現代社会において、
印刷された文字は
不可欠なものです。
均一さは書道の基礎
均一さは書道にとって
凄く大切なことです。
古典の文字にも
均一さの美しい文字があります
例えば楷書の名作である
「九成宮醴泉銘」や
「雁塔聖教序」などは、
非常に整った均一な美しさを
持っています。
この均一さがあるからこそ、
文字全体に品格と安定感が
生まれるのです。
特に楷書においては、
点画の長さや角度、
間隔の均一性が重要です。
これは書道の基礎であり、
初心者が最初に学ぶべき
要素でもあります。
均一さを勉強するには
明朝体は確かに良い素材だと
思います。
文字の骨格や構造を
理解する上で、
明朝体の持つ幾何学的な美しさは
参考になります。
しかし書道は
それだけじゃない
書き文字にはある程度の
均一さは必要ですが、
必要以上に均一になっていると
「書」としてはダメだという
ことです。
あまりにも均一だと思ったら
線質を変えたり、
わざと角度を変えることが
必要なのです。
書道には「拙速」という
言葉があります
完璧すぎる美しさよりも、
多少の不完全さがある方が
人間味があり、
味わい深いという考え方です。
【問題提起】
下手な賞状書きが
大看板を出す現実
印刷のように整った文字の
落とし穴
賞状書きを専門にする会社の
文字によく見られる現象ですが、
まるで印刷したかのように
整った文字は、
一見すると美しく見えますが、
そこには書道本来の
生命力や息遣いがありません。
特に問題なのは、
下手な賞状書きが
大看板で自慢されることです。
これはとても嫌です。
下手くそなのに自分で上手いと
言っているような物です。
基礎のない看板に
憤慨した日
街中で「賞状書きます」という
看板を見かけることがありますが、
その看板に書かれた文字を見ると、
基礎がまったくできていないことが
一目瞭然です。
線に勢いがなく、
字形のバランスも悪い。
それなのに堂々と看板を
掲げているのを見ると、
書道に対する冒涜だと
感じてしまいます。
ぼくが葬儀や看板を書いているとき、
賞状筆耕士を取ったという
じいさんが来て、
下手くそな看板を書いていて、
自分は一流だという姿勢に
酷く憤慨した覚えがあります。
全く三流で基礎が
出来ていませんでした。
賞状筆耕士1級は
眉唾物だと思っています。
文字がでかくなればなるほど
アラが見えてくる物です。
お客様は書道の専門家では
ないため、
その違いがわからないかも
しれません。
しかし、本物と偽物の違いは、
必ず伝わるものだとぼくは
信じています。
本当の「上手い」とは
あれは不健康な状態なので、
真似しないようにしたいものです。
書道における「上手い」とは、
単に整っているという
ことではありません。
その人の個性や感情、
そして筆の勢いが感じられることが
大切なのです。
基礎がしっかりしていない人ほど、
派手な看板で客を集めようと
します。
本当に実力がある人は、
看板に頼る必要がないのです。
計算されたバランスの崩し方、
意図的な不完全さの演出。
これこそが書道の奥深さだと
思います。
例えば王羲之の「蘭亭序」は、
完璧に整った文字では
ありませんが、
だからこそ千年以上も
人々を魅了し続けています。
文字一つ一つに表情があり、
書き手の息遣いが
感じられるのです。
【まとめ】
現代における書道の在り方——
『べらんめい』が教えてくれたこと
基礎があるからこそ崩せる
ぼくは今、字を書く時に
あまりにも整いすぎていると
感じたら、
わざと線の方向性をずらしたり、
線の質を変えたりします。
それは書道を長年やっていないと
出来ないことです。
基礎がしっかりしているからこそ、
意図的に崩すことが
できるのです。
これは料理でも同じで、
基本を知らずに創作料理は
作れません。
古典を現代に活かす
書道を続けていても、
いろいろな方向から学ぶべきだと
思います。
古典が命というわけでは
ありません。
現代に合わせて古典を
解釈する必要があるのです。
デジタル全盛の今だからこそ、
手で書く文字の価値が
再認識されています。
しかしそれは単なる
懐古趣味ではなく、
現代の感性で古典を
捉え直すことが
求められています。
若い世代の中には、
筆で文字を書いたことがない人も
増えています。
だからこそ、書道の魅力を
現代的な方法で伝える
必要があります。
SNSで作品を発表したり、
デジタルツールと組み合わせたり
することも、
一つの方法だと思います。
AIに負けない
「人間の手」
こういったことが
わかっていないと、
活版印刷がデジタルに
変わったように、
書道もデジタルに
駆逐されてしまうでしょう。
AIが文字を生成する時代に
なっても、
人間の手が生み出す「ゆらぎ」や
「温かみ」は、
決して機械には真似できない
ものです。
コンピュータは完璧な文字を
生成できますが、
人間の手が生み出す偶然性や、
その瞬間の感情の揺らぎは、
プログラムすることが
できません。
NHK『べらんめい』の
書作品やセットの文字が
心を打ったのは、
そこに職人の呼吸が
刻まれていたからです。
完璧ではないかもしれない。
でもそこに「生きた人間」がいる。
温故知新——
55年が教えてくれたこと
温故知新。
古きを学び、新しきを知る。
それが現代の書道家に
求められる姿勢だと、
ぼくは55年の経験から
確信しています。
書道は単なる技術ではなく、
生き方そのものだとぼくは
思っています。
一枚の半紙に向かう時間は、
自分自身と向き合う時間でも
あります。
55年間作品を残さなかったことに、
後悔はありません。
なぜなら、書道で学んだことは、
作品という形ではなく、
ぼくの人生そのものに
刻まれているからです。
👇こちらの記事もごらん下さい👇
書道上達法|あて線で字が劇的に整う【筆耕プロが教える秘密】
https://fujii-shobou.com/2025/10/28/calligraphy-atesen-guide/
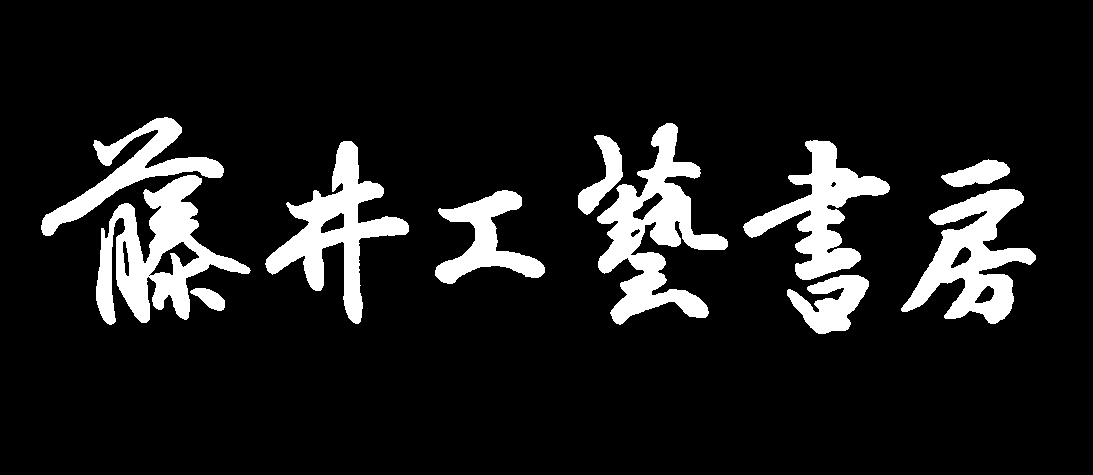
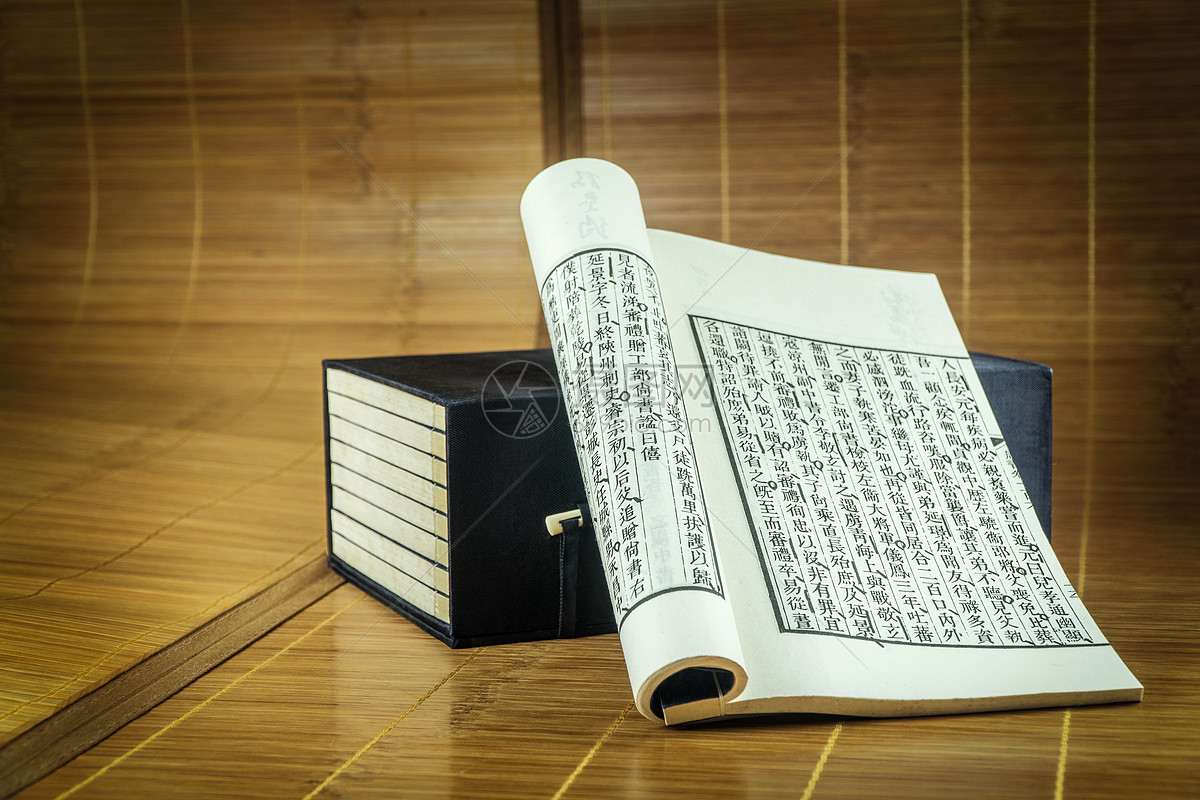

コメント