あなたは字を書くとき
あて線を書いていますか?
|書道上達の隠れた秘密【結論】あて線を使えば字は劇的に整う
書道を始めたばかりの方、
または長年書道をやっているのに
なかなか字が整わない方に
質問です。
あなたは字を書くとき、
「あて線」を使っていますか?
実は、この「あて線」こそが、
書道上達の隠れた秘密なのです。
筆耕のプロとして数万枚を
書いてきたぼくが断言します。
あて線を意識するだけで、
字は驚くほど整います。
あて線とは何か?
|初心者用下敷きの秘密
あて線の基本
あて線とは、
文字を書く際の基準となる
補助線のことです。
これは初心者用の下敷きに
印刷されています。
例えば二玄社の法帖シリーズには、
付録としてあて線入りの
下敷きが付いてきます。
この下敷きには:
横線(字の高さの基準)
縦線(字の中心の基準)
マス目(字の大きさの基準)
が印刷されており、
その上に半紙を置いて
書くようになっています。
なぜ必要なのか
答えは単純です。
字が整うからです。
特に二玄社の法帖シリーズでは、
あて線の上に法帖のお手本が
書いてあります。
ですから:
字の大きさを揃えられる
字の中心を取りやすい
行の揃い方がわかる
字間のバランスが見える
初心者がまず身につけるべきは、
この「整える感覚」なのです。
一般の書道教室はあて線を教えない
書道教室の盲点
ぼくは何カ所か
書道教室に通っていますが、
あて線の上に書けとは
言われたことがありません。
なぜでしょうか?
理由は:
沢山書歴を重ねた人は
もう必要ないと考えている
芸術性を重視するため
自然に書けることを
良しとする風潮
しかし、これは初心者にとって
大きな問題です。
基礎ができていないのに、
自由に書かせても
上達しないからです。
あて線を書くからと言って恥ずかしいとか
思うことはありません。
筆耕・ビジネス書道では必須
一方、筆耕やビジネス用の
書道を教えるところでは、
必ずあて線を書けと
言われます。
書く洋紙の上に
薄い4Bの鉛筆であて線を
書くのです。
その上で考えるのは:
字の中心はどこか
どの線が長いのか
字の間隔をどのくらい開けるのか
全体のバランスはどうか
実用の書道では、
整っていることが最優先だからです。
【実例】後輩指導で
証明されたあて線の威力
書道教室に通っていた後輩
ぼくは葬儀用筆耕会社で
2人の後輩を育てました。
そのうち1人は、
書道教室にも通っていたそうです。
ある日、彼が葬儀用の看板を
書いているのを見て、
ぼくは気づきました。
「まっすぐ書くことを意識していないな」
文字の中心の意識も薄いのだと感じました。
彼の字は:
行が曲がっている
字の大きさがバラバラ
中心がずれている
書道教室で習っているのに、
基本的な「整える感覚」が
身についていなかったのです。
あて線指導を開始
そこでぼくは、
書く洋紙の上に定規で
きっちり測って
あて線を書くことを
指導しました。
最初は戸惑っていた彼ですが、
ぼくは厳しく言いました。
「書道教室では教えてくれないだろうが、プロの仕事では必須だ。
まずはあて線を正確に引け」
毎朝、仕事が始まる前に
30分の練習時間を設けました。
洋紙にあて線を引き、
その上に葬儀用の文字を
書く練習です。
練習すること1ヶ月。
段々と字が整ってきたのです。
元々書道に関心があった彼は、
センスがありました。
ただ、「整える基準」が
なかっただけだったのです。
サイズ別のあて線指定
ぼくは洋紙に合わせて、
あて線の大きさを指定しました:
4尺(約120cm)
6尺(約180cm)
8尺(約240cm)
12尺(約360cm)
18尺(約540cm)
20尺(約600cm)
字を書く人が異なるので
全く同じようにはなりませんが、
仕上がりは大体同じ寸法に
なるのです。
これが、プロの仕事としての書道です。
葬儀という厳粛な場で使われる
看板ですから、
ガタガタした文字では
失礼にあたります。
だからこそ、あて線を使って
きっちり整える必要があるのです。
彼の成長を見守る日々
2ヶ月が経った頃、
彼が上手くなってきているのを
見てぼくは思いました。
書道塾では相当
段位級位が上がっているのだろうと。
実際、彼の字は見違えるほど
整ってきていました。
行は真っ直ぐになり、
字の大きさも揃い、
全体のバランスも良くなっています。
ぼくの目から見ても、
これならプロの仕事として
十分に通用するレベルでした。
驚きの結果
ある日、ぼくは後輩に聞きました。
「書道教室の進級とか段位が変わっただろう?」
彼は笑ってぼくにお礼を言いました。
「おかげさまで飛ぶ勢いで段位が上がりました」
なんと:
2段位、3段位と飛ぶように上がり
師範級になってしまった
というのです。
ぼくの指導方法は
間違っていなかった。
書道教室では教えない
「あて線」という基本を
徹底的に叩き込んだことが、
彼の急成長につながったのです。
彼は書道教室の先生にも
「最近、急に上手くなったね」と
驚かれたそうです。
先生は彼が葬儀会社で
あて線指導を受けていることを
知りませんでした。
職場の人間関係と指導の限界
先輩には教えられない悲しさ
実はぼくには、
もう一つの悩みがありました。
先輩には教えられないのです。
職場には、ぼくより年上の
先輩が何人かいました。
彼らの作品を見ると、
正直なところ
ガタガタしていて
見苦しいものでした。
行は曲がり、
字の大きさはバラバラ、
中心も取れていない。
「あて線をうまく使えばもっと良くなるのに」
ぼくは何度も思いました。
でも、言えませんでした。
年功序列の壁
日本の職場には、
年功序列という暗黙のルールがあります。
後輩が先輩に
「こうした方がいいですよ」と
教えるのは、非常に難しいことです。
特に、先輩が長年書道を
やってきた場合、
プライドもあります。
「俺の方が経験が長い」
そう思われてしまえば、
関係が悪くなるだけです。
後輩だから指導できた
だからこそ、
後輩だから指導できたのです。
後輩は素直に聞いてくれます。
「先輩、どうすれば
上手くなりますか?」
この言葉があるからこそ、
ぼくは全力で教えることが
できました。
先輩の作品がガタガタなのを見るたびに、
ぼくは歯がゆい思いをしましたが、
それでも黙っているしか
ありませんでした。
あて線の書き方、捉え方が悪いのです。
※実際には品行方正な先輩ですが、
ぼくは耐えられなくて、正直に
字の中心や行の方向が激しく曲がっていることを指摘して
関係を悪化させてしまいました。
書道に関してはウソをつけません。
ぼく人って関係を悪化させることはつらいことでした。
2人目の後輩への指導
新しい挑戦
こうして、
2人目の後輩も
指導してゆきました。
2人目の後輩は、
書道系の大学の出身ですが、
プロの字を書く経験が全くない状態でした。
1人目の後輩は
書道教室に通っていたので
基礎はありましたが、
2人目は完全にゼロからです。
最初は不安でした。
「プロ書道未経験者に、
葬儀用の看板が書けるように
なるのだろうか?」
でも、1人目の成功体験が
ぼくに自信を与えてくれました。
あて線指導は、
未経験者にこそ効果的だと
気づいたのです。
ゼロから始める強み
プロ書道未経験者でしたが、
書道系大学出身とあって
変なくせがありました。
書道系大学出身の人は、
「芸術性」を重視する癖が
ついていることがあります。
しかし彼女は、
教えられたことを
素直に吸収します。
2人目の後輩には、
最初から徹底的に
あて線を意識させました。
「まず、定規できっちり測ってあて線を引く。
これができなければ、字は書かせない」
厳しい指導でしたが、
彼は文句を言わずに
従ってくれました。
3ヶ月後の成果
3ヶ月が経った頃、
2人目の後輩の字は、
驚くほど整っていました。
プロ書道未経験から始めたとは
思えないほどです。
1人目の後輩よりも、
成長スピードが遅かったかも
しれません。
なぜなら、
変な癖があったからです。
彼女は古典の木簡や隷書、金文に興味がありました。
ぼくの指導により、
あて線を基準に、
真っ直ぐ、均等に、
バランス良く書く。
これだけに集中できたのが、
良かったのだと思います。
あて線が見えない問題とその解決法
半紙の厚みが関係する
書道教室によって違いますが、
下敷きの上に半紙を置きます。
この時、半紙の厚みが
関係してきます:
半紙が薄い場合:
あて線が透けて見える
書きやすい
初心者向き
半紙が厚い場合:
あて線が見えにくい
書きづらい
上級者向き
重要なのは「意識」
しかし、半紙の厚みよりも
重要なのは:
あて線を意識しているかどうか。
見えなくても、
「ここにあて線がある」と
意識しながら書くのと、
何も考えずに書くのでは、
結果が全く変わってきます。
これは料理と同じです。
レシピを見ながら作るのと、
適当に作るのでは、
出来上がりが違うのと同じです。
ぼくが指導した2人の後輩は、
どちらも常にあて線を
意識していました。
だからこそ、短期間で
劇的に上達したのです。
上達者はあて線が要らない理由
体に染み付いた感覚
本当に上達した人は、
もちろんあて線なんて要りません。
何も書いていない白紙に、
すぐに書いていけます。
なぜでしょうか?
体の中に字のサイズ感が
染み付いているから
出来る技なのです。
これは:
何千枚、何万枚と書いた経験
あて線を意識し続けた練習
失敗と修正の繰り返し
この積み重ねの結果です。
プロの領域
ぼくも筆耕の仕事では、
洋紙にあて線を引きますが、
半紙での練習では
もう引きません。
55年の経験で、
体が覚えているからです。
でも、これは決して
「才能」ではありません。
地道な練習の積み重ねです。
ぼくが指導した2人の後輩も、
いずれはあて線なしで
書けるようになるでしょう。
でもそれは、今、
あて線を徹底的に意識して
練習しているからこそです。
【実践】あて線を使った練習法
初心者の方へ今日から実践してください:
二玄社の法帖を買う
付録のあて線入り下敷きを使う
最初は楷書の法帖がおすすめ
あて線を強く意識する
字の中心がどこか
横線がどこに来るか
字の大きさはどうか
毎日10枚書く
あて線を見ながら
同じ大きさを目指す
1ヶ月続ける
1ヶ月後、必ず変化を感じます。
中級者の方へ書道歴が長いのに字が整わない方:
プライドを捨てる
あて線は初心者用?関係ない
上達のためなら何でも使う
洋紙に鉛筆で線を引く
4Bの薄い鉛筆で
定規できっちり測る
消せるので何度でも練習できる
ビジネス書道の視点を学ぶ
芸術性より実用性
整っていることの価値
プロの基準を知る
書道教室とビジネス書道の
違いを理解する
書道教室の目的:
- 芸術性の追求
- 古典の学習
- 個性の表現
- 段位の取得
ビジネス書道の目的:
実用性の追求
読みやすさ
整った美しさ
仕事として通用する技術
どちらが正しいという
話ではありません。
でも、基礎として
「整える技術」を身につけるなら、
ビジネス書道の視点が
圧倒的に有効です。
ぼくが指導した2人の後輩は、
ビジネス書道の視点を学んだことで、
書道教室での評価も
上がりました。
基礎がしっかりしていれば、
芸術性も後からついてきます。
【まとめ】あて線を
制する者が書道を制す
結論
書道で字のサイズ感が
身についていないうちは、
あて線を意識しましょう。
むやみに書いても
作品はまとまりません。
あて線は:
初心者の必須ツール
中級者の再確認ツール
上達への最短ルート
今日からできること
あて線入り下敷きを買う
二玄社の法帖シリーズ推奨
または自作する
意識を変える
「あて線は恥ずかしい」→「あて線は上達の武器」
1ヶ月間、毎日練習
あて線を見ながら書く
必ず変化が現れる
最後に
ぼくが指導した2人の後輩は、
あて線指導で劇的に
上達しました。
1人目は段位が飛ぶように上がり、
2人目は未経験からわずか3ヶ月でプロレベルに。
あなたも同じことが
できるはずです。
初心者であることを
恥じる必要はありません。
先輩には教えられなかったけれど、
後輩には教えられた。
それは、素直に学ぶ姿勢が
あったからです。
素直に、あて線を使って
上達してください。
それが、55年の経験から
ぼくが伝えたいことです。
👇こちらの記事もごらん下さい👇
べらんめい書道に触発|筆耕士55年が明かす明朝体練習の真実
https://fujii-shobou.com/2025/10/26/calligraphy-55-years-experience/
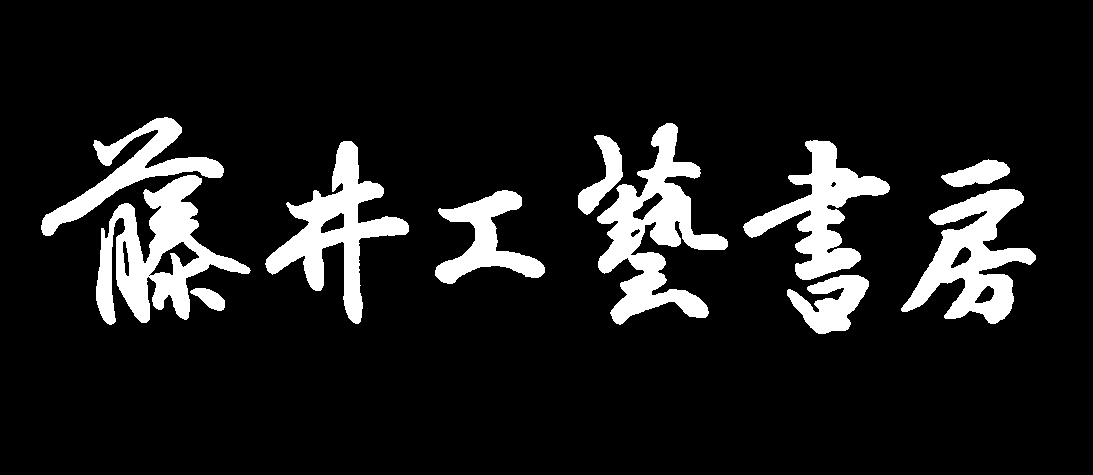



コメント